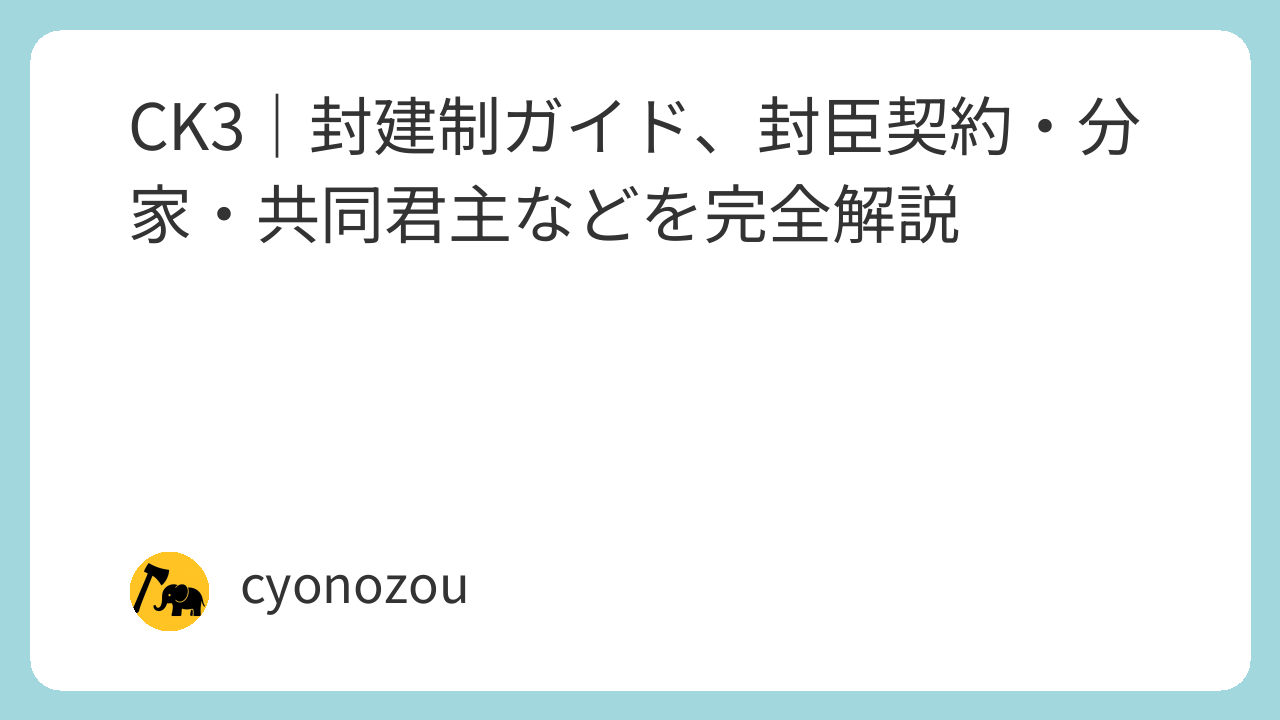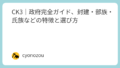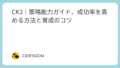はじめに
Crusader Kings III(CK3)では「封建制」は最もスタンダードで歴史的にも馴染みの深い政体の一つであり、領主として領地を統治し、封臣との契約を結びながら支配を広げていくシステムが魅力です。
本記事では、封建制の基本的な仕組み(分家・共同君主・封建契約)から、税収・軍事・契約の操作方法まで、実践で役立つ情報を初心者にも分かりやすく解説します。封建制を採用してプレイする際のメリット・デメリットや、他政体との違いも整理しているので、「どの政体で始めようか迷っている」方にとって有益な内容です。
封建制の内容
ゲーム内では以下のように説明されています。
・分家の結成が可能
・封臣契約を使用します
・王国階級以上の統治者が、成人している自分の子供を共同君主へ昇格させることができるようになる封建政体のもとでは、主君は封臣に所領を与え、徴募兵と税金を支払わせます。具体的な内容は封臣と主君のあいだで個人的に交わした封臣契約で定められます。
分家
「分家」はゲーム内で以下のように説明されています。
王朝には必ず創設家が存在しますが、家長となるために、家の成員は自身の新たな一族、つまり分家を創設することができます。
分家の成員も自由に同じことができるので、いずれは王朝内に枝分かれした家系図ができあがります。
分家は宗家と同じ王朝ですが、独自の家の名前や紋章、家訓を有します。
宗家からすると、容易に同盟を締結できたり、名誉の増加率が上昇するといったメリットがあります。
一方で、内戦や、称号をめぐる争いが生じることがあります。
共同君主
「共同君主制」はゲーム内で以下のように説明されています。
共同君主制は権力の共有の1つで、たとえ時代的に早くとも、封建制統治者が指名後継者を選択することができます。
その代償として統治者は永続的な権力の共有協定を結ぶ必要があり、その結果、共同君主は多くの強権化した摂政と同等の権限を簡単に利用できるようになります。
共同君主は王と皇帝にしか利用できません。
「時代的に早くとも」とあるとおり、好みの者を後継者とすることが可能です。
ただし、指定後継者が全ての称号を相続するわけではありません。共同君主が存在している場合でも、相続法に従って通常通りの相続が行われます。
また、あまりにも長い間共同君主が存在しかつ強権化した場合、指名後継者は、勝手に封臣の称号を剥奪したり、金を横領する可能性があります。
封建契約
以下のように定義されます。
封建契約は、封臣と主君のあいだの義務を定めるものです。
封建制、氏族制、官僚制、遊牧制政体の封臣にはさまざまな義務が用意されており、それぞれの封臣と個人的に交渉を行います。
すべての封臣は自身の義務に応じて、税金と徴募兵の一部を主君に支払います。この貢献度はさらに、要塞建造の権利許可ありなどの「細則」により修正を受けます。
一部の特殊な契約は特定のランクでしか利用できません:
・行軍の契約と軍役代納金の契約:公爵かそれ以上
・バラチン伯爵の契約:伯爵かそれ以上
・城主契約:伯爵のみ属州総督の義務は属州行政とも呼ばれます。
主君と家臣の間で、個人的に締結される契約です。
相手に対するフックを有する場合、契約を修正できる場合があります。
おわりに
封建制は、CK3 における王朝運営の中心になる政体であり、その特徴を正しく理解することで、契約や内政・戦略の選択肢が大きく広がります。分家を活用して王朝を拡張するか、共同君主制で後継問題を緩和するか、封建契約を操作して封臣からの収入を最大化するか――これらの要素をうまく組み合わせることで、封建政体の本領を発揮できるでしょう。この記事の内容が、あなたの CK3 の王朝を強く、そして安定したものにする助けになれば幸いです。他の政体との比較や、封建制の発展・政体変更のタイミングなども別記事で扱っていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。